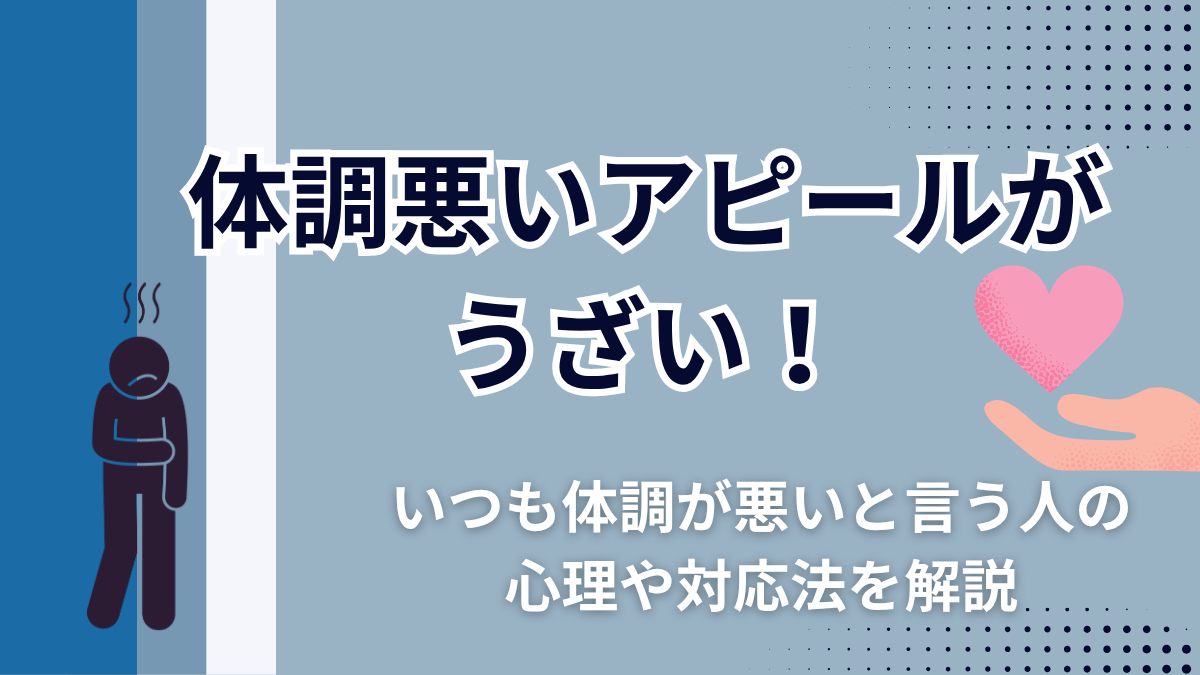「また体調悪いって言ってる」そんなふうに感じてしまう自分に、モヤモヤしたことはありませんか?
体調悪いアピールをする人にうんざりしつつも、「冷たくしたくない」「でも正直、うざい」と心が揺れることもあるでしょう。
この記事では、
- 体調悪いアピールをする人の心理
- うざいと感じる自分の気持ちの正体
- 上手な距離の取り方
を分かりやすく解説します。

読んだあとには、相手に振り回されず、自分の気持ちを大切にしながら穏やかに対応できるようになりますよ。
体調悪いアピールがうざいと感じるとき


体調不良を伝えること自体は悪いことではないですが、その頻度やタイミングによっては、周囲が不快感を抱くことがあります。
体調悪いアピールがうざいと思ってしまう瞬間は、
- 頻度が多すぎる
- 場面を選ばない
- 表現が一方的
といった要素が重なったときに強く感じやすいです。
特に、忙しい職場で頻発したり、SNSで日々「しんどい」といった投稿が続いたりすると、受け止める側の負担感は大きいですよね。
たとえば、同僚が毎週のように「体調が悪い」と言って早退すると、そのたびに残された人がフォローに回ることになるので、少しずつ不満が積もっていきます。
ここでは、どのような時に、体調悪いアピールがうざいと感じるか具体的に解説していきますね。
しつこく繰り返される
最初のうちは心配や気遣いの気持ちがあっても、同じ話が続くうちに「またか」という感情が芽生えやすいですよね。
特に、症状を訴えるだけで改善の行動が見えない場合、疑ってしまうこともあります。
たとえば、週に何度も「頭が痛い」と繰り返していると、周りは対応に疲れてしまい、徐々に距離を置きたくなるケースも。



しつこいアピールは、本人が思っている以上に周囲の人を疲れさせる行為になり得ますよ。
体調を頻繁に伝えられること自体が悪いわけではありません。
ですが、あまりに何度も聞かされたり、言い方によっては「またか」と感じてしまい、素直に心配したり協力する気持ちが薄れてしまうこともあるのです。
職場でのアピール
周囲は気をつかって声をかけたり仕事をフォローしたりするため、どうしても雰囲気や業務の流れに影響してしまうんです。
もちろん、体調を崩すことは誰にでも起こることなので、たまにであれば「大丈夫?」と心配する気持ちも自然に出ます。



しかし、頻繁に繰り返されたり、同じような内容が続いたりすると、正直「またか」と感じてしまうことも。
だからこそ、「いつ」「どのタイミングで伝えるか」を少し意識してもらえると助かる、と思う人も多いでしょう。
SNSでの投稿
SNSは不特定多数に向けた情報発信の場。



毎日のように「しんどい」「頭が痛い」などの投稿が続くと、見る側が疲れてしまいますよね。
最初のうちは心配していた人も、同じような内容が繰り返されるうちに反応が減り、やがてスルーされるようになるケースもよくあることです。
特に、具体的な状況の説明もなくネガティブな言葉ばかりだと、「ただかまってほしいだけでは?」と思ってしまうこともあります。
SNSで状況を共有するのは自由ですが、あまりに頻繁だったり一方的な発信が続くと、正直周囲は負担に。
内容によっては、信頼できる相手に個別で相談してくれたほうが助かる、と感じる人も多いでしょう。



使い分けを意識してもらえると、周囲も気をつかいすぎず、関係を保ちやすくなりますね。
周りに悪い影響を与える
主な影響は以下の3つです。
- 心理的な負担
- 繰り返し聞かされることで、「またその話か」と感じやすくなる。
- 気づかないうちにストレスや疲労感が溜まり、対応する側の余裕がなくなる。
- 職場での実務的な負担
- 頻繁に欠勤や早退があると、業務のしわ寄せが他のメンバーに集中する。
- 不満や不信感が積み重なり、チーム内の雰囲気が悪化する要因になる。
- 家庭での精神的な圧迫感
- 毎日のように「しんどい」と言われ続けると、家族も次第に対応に疲弊してしまう。
- 常に誰かが不調を訴えていると、周囲が気を遣い過ぎて息苦しさを感じるケースもある。
体調の話は必要な場面もあります。
ですが何度も繰り返されたり言い方が一方的だと、正直「またか」と感じてしまい、人間関係に微妙な影響が出ることも。



伝え方やタイミングのバランスがうまく取れていないと、周囲との関係がぎくしゃくしやすくなるのです。
いつも体調が悪いと言う人の心理


いつも体調が悪いと繰り返す人の中には、単なる不調の訴え以上の心理が隠れていることがあります。
背景を理解することで、余計なイライラを減らし、冷静な対応がしやすくなりますよ。
主な心理的背景には次のようなものがあります。
- 心配してほしい・注目されたい
- 察してほしい
- 自己肯定感が低い
- 無意識
こうした背景を知らずに、表面的な発言だけを見て「うざい」と決めつけてしまうと、対応を誤り関係がぎくしゃくすることも。
発言の裏にある感情や理由を理解することで、ストレスを減らし、関係を保ちながら自分を守ることができるでしょう。
ここでは、隠された心理を一つずつ詳しく解説していきますね。
心配してほしい・注目されたい
体調不良を伝えることで、周囲の優しさや気遣いを引き出し、自分の存在を確認しようとする心理です。
体調不良を伝えることで「気にかけてもらえる」という安心感を得ようとしているんですね。
ただし、あまりに頻度が多いと「かまってほしいだけ」と受け取られてしまい、逆に距離を置かれることも。
心配してほしい気持ちは自然なことなので、その背景を理解しておくと、冷静に対応しやすくなりますよ。
察してほしい
- 体調不良をうまく言葉にできない
- 直接的に助けを求めるのが苦手
- 周囲に気づいてもらいたい
たとえば、「今日も頭が痛い」とだけ言う人は、実は
- 「無理しないで」
- 「早めに休んで」
といった言葉を待っている場合があります。
心理を理解しておくことで、必要以上に振り回されず、穏やかな対応ができますよ。
自己肯定感が低い
- 自分に自信が持てない
- 周囲の優しい言葉で安心したい
- 失敗や不安を体調不良でカバーしたい
たとえば、仕事で落ち込んでいるときに「体調が悪い」と言うことで、責められるのを避けたり、誰かに受け止めてもらいたい気持ちが働いていることがあります。
悪意ではなく、防衛反応として出ているケースが多いんです。
背景を理解しておくと、相手を責めるより冷静に向き合えるようになりますよ。
無意識の場合も
- 「疲れた」「しんどい」が口癖になっている
- 周囲への影響を自覚していない
- 習慣的にネガティブな言葉を口にしている
職場のパートのおばちゃん(先輩)が出勤するたび体調悪いアピールしてきてうざい、あんたの体調いい日はいつなん?そんな辛いならしんどいしんどい言ってないで帰れば?てかやめれば??
— ウシさんは生きづらい (@ushimadao) October 1, 2024
悪気はないので注意されてもピンとこないことが多く、対応が難しいこともあります。
適切な距離を保ちつつ、必要に応じて伝え方を工夫するのがポイントですよ。
体調悪いアピールへの基本的な対応法


体調悪いアピールに直面したときは、感情的に反応せず、冷静に対処することが大切です。
相手の言動に振り回されると、不要なストレスが増えるだけでなく、関係性もこじれやすくなります。
以下の基本的な対応の流れを押さえておくと、無理のないコミュニケーションがとりやすくなりますよ。
- 冷静に対応する
- 距離感と境界線を保つ
- 一旦受け止める
- 医療機関や上司に相談する
ここではそれぞれについて詳しく見ていきますね。
冷静に対応する
何度も繰り返されると苛立ちが募りやすいですが、感情的に反応すると状況が悪化することがあります。
相手の発言の背景には心理的な要因が隠れている場合も多いです。



頭ごなしに否定したり、強く反論したりすると関係がこじれる原因にも。
たとえば、毎日のように「しんどい」と訴える人に対して「またそれ?」と突き放すような対応をすると、相手は傷ついてさらにアピールを強めるでしょう。
感情に流されず、淡々とした対応を意識することが、不要なトラブルを防ぐポイントになりますよ。
距離感と境界線を保つ
感情的に巻き込まれすぎると、聞き手側の心が疲弊してしまい、冷静な対応が難しくなるからです。
たとえば、相手が毎回長時間にわたって体調不良を訴える場合、最初のうちは親身に聞いていても、次第に負担が積み重なってしまうことも。
そんなときは、
- 必要なときにだけ対応する
- 反応の仕方を少し抑える
など、無理のない関わり方を意識するとよいでしょう。
距離感や境界線をしっかり持つことで、相手との関係を悪化させずに、自分の心も守りやすくなりますよ。
一旦受け止める
感情的に反応するよりも、相手の話を聞くことで、防衛的な態度を和らげ、落ち着いたやり取りができますよ。
具体的には、
- 「大変だね」
- 「無理しないでね」
といった短い共感の言葉を添えるだけでも、相手の気持ちを和らげる効果も。
話を聞いた上で、必要に応じて距離を取りながら対応しましょう。
そうすることで、自分自身の負担を増やさずに、相手との関係を良好に保つことができますよ。
医療機関や上司に相談する
周囲だけで抱え込むより、客観的な視点を入れることで、冷静に対応しやすくなりますよ。
たとえば職場なら、健康相談窓口や産業医に話を通しておくと、必要なサポートや対策がスムーズに進みやすいでしょう。
本人にとっても周りにとっても、状況を整理するきっかけになります。
家庭でも、医療機関で診てもらうことで、症状の確認や具体的なアドバイスを受けられ、自己判断で迷走するリスクを減らせますよ。
無理せず適切なサポートを得ることで、関係をこじらせずに落ち着いた対応がしやすくなるでしょう。
職場での体調悪いアピールへの対応法


職場で体調悪いアピールが続くときは、感情的にならず、状況に合わせて落ち着いて対応しましょう。
業務への影響も出やすいため、相手の様子や頻度を見極めながら、対応の仕方を柔軟に変えるとスムーズですよ。
基本的には、以下のように使い分けるとよいでしょう。
- 軽い不調・一時的な訴え
- 短い共感の言葉で気持ちを受け止める。
- しつこい・過剰なアピール
- 必要に応じて淡々と注意や対応の線引きをする。
- 深刻そうな場合
- 上司や専門機関への相談も検討する。
また、相手の性別や年齢、立場によって伝え方を少し変えるのも効果的です。
たとえば男性にはストレートな言い方が響く一方で、若い女性社員には共感を多めにするとスムーズに伝わることも。
状況に合わせて対応を工夫することで、無用な対立を避けながら、職場全体の雰囲気を良好に保ちやすくなりますよ。
スルー・共感・注意の使い分け
「スルー」「共感」「注意」を上手に使い分けると、無用なトラブルを避けながら関係を保ちやすくなります。
たとえば、ちょっとした一言程度の体調不良には、軽く共感の言葉を返すだけで十分な場合が多いです。
深刻な話ではなく、単なる口癖や日常的なぼやきに近いときは、あえて深く踏み込まずにスルーするのも。



私も慢性的に肩こりがあるため、夕方「肩がこる」と無意識にぼやいてしまうことがあります。
一方で、同じ内容が何度も繰り返されたり、周囲への影響が大きいと判断される場合は、やんわりと注意を促しましょう。
そうすることで、感情的な衝突を避けながら、コミュニケーションを取ることができますよ。
男性・おじさんタイプへの対応
年齢や立場の影響で、ストレートな注意はプライドを傷つけ、話がこじれてしまうこともあります。
たとえば
- 「それは大変でしたね」
- 「無理しないでくださいね」
と一言添えるだけでもOK。
話を頭ごなしに否定するより、さらっと受け止めるだけで相手の安心感はぐっと増しますよ。
もし頻度が多く、周囲への影響が気になる場合は、感情的にならず事実ベースで伝えましょう。
敬意を保ちながら、適度な距離感で冷静に伝えることで、余計なトラブルを避けつつ、職場の空気を保ったまま対応できますよ。
女性社員への対応
感情がこもった言い方になることも多いので、いきなり業務の話をすると冷たく感じられてしまうこともあります。
まずは
- 「大丈夫ですか?」
- 「無理しないでくださいね」
と一言かけるだけで、安心感が生まれます。
それから、具体的な対応に入るのがスムーズですよ。
業務への影響を抑えるためには、状況を丁寧に確認して、必要に応じてサポートの提案をしましょう。
引き継ぎやスケジュール調整を提案するのも効果的。
共感と実務対応のバランスをうまく取ることで、相手との信頼関係を保ちながら、職場全体が気持ちよく動ける環境をつくることができますよ。
自分のストレスをためない工夫
相手に気を遣い続けたり、対応を一人で抱え込んでしまうと、心身への負担も大きくなってしまいますよね。
だからこそ、自分を守る工夫も大切です。
- 一人で抱え込まず、業務ローテーションを活用して負担を分散する。
- 上司や人事に相談して、組織として対応できる仕組みを整える。
- 相談窓口や健康管理の仕組みを活用する。
また、自分自身のストレス状態を日ごろから意識しましょう。
必要なときは一歩距離を取ってリフレッシュする時間を持つことも重要です。
無理をしすぎず、チーム全体でサポートし合える環境を整えることが、長く続けられるコツですよ。
夫婦・家庭での体調悪いアピールへの対応法


夫婦・家庭での体調悪いアピールは、「相手がどんな気持ちで言っているのか」を理解しようとする姿勢が大切です。



家庭内で「体調悪い」という言葉を聞くと、ついイラッとしてしまうこと、ありますよね。
夫婦・恋人・親子といった近い関係では、ちょっとした言葉や態度が誤解につながることも多いもの。
いきなり否定したり、軽く受け流してしまうと、「わかってくれない」と感じさせて関係がこじれてしまうこともあります。
対応の基本は次の3ステップです。
- まずは相手の気持ちをしっかり聞く。
- お互いの境界線を意識する。
- 冷静に話し合う流れをつくる。
感情に流されず、落ち着いて対話することで、お互いを尊重しながら現実的な解決策を見つけやすくなります。
ちょっとした意識の違いが、家庭内の空気を変えるきっかけになりますよ。
夫・妻・彼氏彼女・親の心理を理解する
「体調悪い」と一口に言っても、その背景は相手によってさまざまです。
旦那の体調悪いアピールがなかなかうざい 私が鼻水垂れてようが頭痛かろうが普段とかわらん生活やのに自分になったらこれか てか旦那から私も息子もうつされてる気しかせんくてそれもだるい 息子の為にもちゃんと予防してくれよ
— しゅが@7y♂+3y♂ (@sgsg0902) March 29, 2021
- 夫・妻の場合
- 家事・育児・仕事の疲れがたまっていることが多い。
- 恋人の場合
- ちょっと甘えたい気持ちや、もっと気にかけてほしいという思いが隠れていることも。
- 親の場合
- 加齢や持病など、実際の体調変化が関係していることが多い。
それぞれ立場や状況が違うので、求めている反応も変わってきます。



私は出産後睡眠不足が重なった時、夫に「体調悪いアピール」をしてしまったことがあります。
感情的に受け止める前に、「この言葉の裏にはどんな気持ちがあるんだろう?」と一度立ち止まって考えてみましょう。
そうすることで、よりスムーズなコミュニケーションにつながりますよ。
過剰に背負い込まない
でも、全部を抱え込むと心も体も疲れ切ってしまい、共倒れになってしまうこともあります。
自分の健康を守ることも、家族を支えるうえで大切な役割です。
無理をしないための工夫としては
- 家事・育児の分担を家族で話し合って明確にする。
- 必要に応じて親族や地域のサポートを頼る。
- 「自分だけで解決しよう」と思い込みすぎない。
1人で抱え込まず、家族や周囲と協力して無理のない体制を整えましょう。
それが結果的に長く良い関係を続けるコツですよ。
冷静に気持ちを伝える・話し合う
でも体調悪いアピールが頻繁に繰り返されると、ついイライラして感情的にぶつかってしまうことがありますよね。
伝えるときは、次のポイントを意識すると効果的です。
- 感情ではなく、事実と希望を短く具体的に伝える。
- 相手を否定せず、自分の立場や状況もきちんと話す。
- 一度で解決しようとせず、定期的な話し合いの時間を持つ。
冷静な対話の積み重ねが、信頼関係を守るカギになりますよ。
病気とアピールを見分ける
チェックしておきたいのは
- 症状がどのくらい続いているか。
- 病院を受診しているか、診断や医師の意見があるか。
- 生活への影響が出ているかどうか。
症状が長引いている場合や生活に支障がある場合は、医療機関の受診を勧めるのも一つの方法です。
一方で、診断もないまま繰り返される場合は、生活習慣や環境の見直しが必要なことも。
事実をもとに見極めることで、必要なサポートとそうでない部分を分け、適切な対応ができるようになりますよ。
体調悪いアピールをうざいと感じる自分との向き合い方


「体調悪いアピールがうざい」と思ってしまうのは、自分の過去の経験や期待、価値観が影響しているケースがあります。
「体調悪いアピールがうざい」と思ってしまうと、ついその感情を押し込めようとしたり、自己嫌悪になったりすることがありますよね。
でも、その感情にはちゃんと理由があることが多いんです。
たとえば以下のケースがあげられます。
- 過去に誰かの体調不良で自分の負担が増えた経験がある。
- 「体調が悪くても我慢するのが普通」という価値観がある。
- 相手に「もっと協力してほしい」という期待がある。
感情を我慢するのではなく、「なぜ今、イラッとしたのか?」を丁寧に見つめ直すことで、対応がぐっとしやすくなりますよ。
この流れを意識することで、余計なストレスを抱えずに、相手とも健やかな関係を保てるようになりますよ。
なぜイラッとするのかを客観視する
イラッとする気持ちは、決して「悪い感情」ではありません。
ただ、そこにどんな背景があるのかを理解しないままにすると、必要以上に感情がふくらんでしまうこともあります。
たとえば以下のようなケースです。
- 自分が忙しいときに聞くと、「今はそれどころじゃない」と反射的に思ってしまう。
- 過去の嫌な経験が重なり、無意識に強く反応してしまう。
こうした感情は、頭の中だけで考えると整理しにくいもの。
「何が引き金になったのか」を客観的にとらえることで、余計なイライラを手放しやすくなり、冷静な対応への第一歩につながるでしょう。
過去の経験や価値観が影響している
たとえば以下のようなケースです。
- 以前、職場で誰かの体調不良が続き、自分に仕事が集中した経験がある。
- 家庭で「我慢が当たり前」という価値観の中で育った。
- 「また同じことになるのでは」という警戒心がある。
こうした経験や考え方が、現在の状況と重なって反応を強めることがあります。
でも、過去と今は別の出来事。
自分の心のクセを知っておくと、相手にも穏やかに向き合いやすくなりますよ。
期待とのギャップを理解する
たとえば以下のようなケースです。
- 「チームの一員として当然協力してくれるはず」と思っていた人が頻繁に休む。
- 「自分ばかりが頑張っているのに」という気持ちが募っている。
こうしたとき、相手が悪意を持っているわけではなく、単にこちらの期待が高すぎる場合もあります。
相手の状況や能力を踏まえて「この人にはここまでを期待しよう」とラインを調整すると、無用なストレスを減らせます。
期待を現実的に見直すことは、気持ちをラクにする大切なステップですよ。
感情を整理して冷静に対応する
おすすめに以下の方法があります。
- 強い感情を感じたら、まず深呼吸や短い休憩で一呼吸おく。
- 感情が落ち着いてから、事実をもとに冷静に対応する。
- 自分がイライラしやすいパターンを知っておく。
日ごろから「自分の感情をケアする」習慣を持っておきましょう。
そうすることで、人間関係のトラブルを防ぎ、心も穏やかでいられますよ。
体調悪いアピールがうざい!心理と対応法まとめ
体調悪いアピールをうざいと感じるとき、そこには「相手の心理」と「自分の心理」の両方が関係しています。
どちらも理解しておくことで、イライラを減らし、冷静に対応しやすくなります。
体調悪いアピールの裏にある心理4タイプ
- 心配してほしいタイプ
- 孤独感や承認欲求が背景にあり、優しさを求めている。
- 察してほしいタイプ
- 直接的な表現が苦手で、反応を期待している。
- 自己肯定感が低いタイプ
- 人から受け入れられることで安心感を得たい。
- 無意識タイプ
- 悪気なく口癖のように「疲れた」「しんどい」と言っている。
うざいと感じるときの心理・場面
- 忙しいときに何度も聞かされる
- 自分の時間や余裕が奪われる感覚になり、負担に感じやすい。
- 過去に自分が我慢してきた経験がある
- 「自分のときは助けてもらえなかったのに」という感情が刺激される。
- 相手への期待と現実のギャップ
- 「このくらいは自分でやってほしい」という思いと、相手の言動がかけ離れているとイラ立ちが募る。
- 構ってほしいだけに見える
- 具体的な行動が伴わず、ただの「かまってアピール」のように感じられると、反応に困る。
対応のポイント
- 感情を否定せず「今の自分の反応」を理解する。
- 相手の背景を知って、むやみに反応しすぎない。
- 状況に応じて、共感・スルー・線引きを使い分ける。
- 無理せず、関係を保てる距離感を意識する。
このようにお互いの心理を知ることで、「うざい」と感じる瞬間も少しずつ冷静に受け止められるようになりますよ。